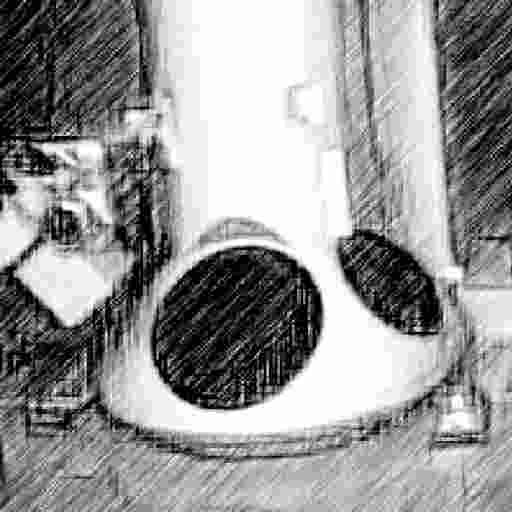― 安全性と利便性の両立を前提とした当室での取り組み ―
本ページでは、分析電顕室において当室が実際に導入・運用している、実験装置とネットワーク環境の活用事例をご紹介します。
実験装置をネットワークに接続することには慎重な判断が求められます。安全性を最優先する運用も当然尊重されるべき方針ですが、適切な設計と管理を行うことで、リスクを抑えながら利便性を高めることも可能です。
当室では、限られた人的リソースの中で運用効率を改善するため、IT/IoT/ICTの活用を進めてきました。ここでは、研究室単位でも応用可能な取り組みを中心に概要をご紹介します。具体的な方法については、今後、個別ページで順次ご案内していく予定です。
装置制御PCからのデータ取り出し
古い制御PCやスタンドアロン構成の装置でも、安全な方法でネットワーク経由のデータ転送を行うことが可能です。USBメモリやCDR等のライトワンスメディアを使わずにファイルを取得する方法を実践しています。
NASによる実験データの保存と外部アクセス
各装置に設置されたNAS(ネットワーク対応ストレージ)に実験データを保存することで、USBメモリなどの物理メディアによる持ち出しを不要としています。研究室のPCやVPN経由での外部アクセスにより、自分のデータへ安全かつ迅速にアクセスできます。
実験装置の画面を遠隔モニタ
VNCやリモートデスクトップを用いて、研究室のPCから実験室内の装置制御PCの画面をモニタできます。装置に常時付き添う必要がなくなり、複数装置の管理にも役立っています。
リモート立会実験の工夫
Zoomや他の画面共有ツールを利用し、実験画面を遠隔で共有することで、装置利用者と支援者が別室・別拠点にいても協働して実験ができるようにしています。
VPNを活用した遠隔モニタ
外出先や自宅から実験装置の状態を確認したい場合、VPN接続により安全に装置画面へアクセスすることができます。使用状況の確認や長時間測定の監視などに応用しています。
大容量ファイルの共有(Filesender(独自運用))
インターネットを活用して、装置から得られた画像や動画等の大容量データを安全に送信・共有する仕組みを整えています。外部研究者やゲスト利用者へのデータ送付に使用しています。
予約システム(+装置使用ログ)
当室で運用中の予約システムは、研究室単位での導入にも応用可能です。利用ログとの連携によって、利用状況の把握や装置トラブル時の対応にも役立っています。
IoTセンサによる実験室モニタ
実験室内の温度・湿度・電源状態などをIoTセンサで常時モニタリングしています。環境変化のログを蓄積し、必要に応じて空調設備や機器へのアラート連携を行うことで、安定した実験環境を維持しています。
装置ステータスの自動記録
装置制御PCに簡易スクリプトを組み込み、装置の稼働状況・ステータス履歴などを定期的に記録しています。ユーザーの操作履歴やトラブル発生時の分析にも活用できます。
これらの取り組みは、専門のICT部門によるものではなく、現場においてDIY的に工夫してきた内容です。今後、より詳しい事例紹介や手順なども順次公開していく予定です。
当室の取り組みの紹介が、運用改善の参考になれば幸いです。